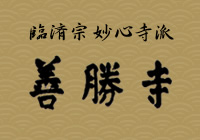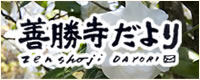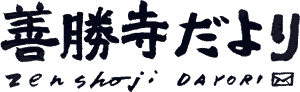 |
善勝寺だより 第124号令和5年9月12発行発行責任者 明見弘道 (2ページ) |
 |
|---|
禪とは何か
皆様は「鈴木(すずき)大拙(だいせつ)」との名前を聞かれたことがおありでしょうか。
本名は「貞太郎」1870年、金沢市生まれ。東京帝国大学在学中に円覚寺にて参禅し、大拙の道号を受ける。97年渡米「禅と日本文化」を発表。
帰国後、学習院、東京帝国大学、大谷大学で教鞭を執るほか、英文雑誌を創刊し、海外に仏教や禅思想を発信した。
1936年、世界信仰大会に日本代表として出席。イギリス、アメリカの諸大学で教壇に立った。66年没。「鈴木大拙全集」全40巻(岩波書店)がある。
以上「角川文庫」新版カバーより
この大拙氏が、昭和2年から3年に大阪妙中寺で行われた計10回の講演の記録に基づいて昭和五年に出版されたのが初めで、出版社が変わっても今日に至るまで版を重ねてきました。
私の手元にある「禪とは何か」は角川文庫のものです。
さて、私は京都の花園大学で仏教学および禅学を学び、禅を世界に広めた人と言えば鈴木大拙と当たり前のことでした。禅学の講義に大拙の名前が出てこないことはないほどでした。
当然入門書ですので「禪とは何か」も読んだと思いますが、ほとんど記憶にありません。そして50年ぶりにこの本を読んだのですが1回目はスラスラ読めました。
ところがこれはちょっと待てよ、となってからは、2回目、3回目と益々これは奥深いなと思うようになり、何度も同じ所を読むようになりました。
ちょうどその頃、鎌倉円覚寺の横田南嶺管長老師が「鈴木大拙一日一言」
横田南嶺監修・蓮沼直應編(致知出版社)を送って下さいました。
今後、この2冊の本を参考にして、「鈴木大拙の禪とは何か」を皆様方に紹介できたらいいなと思っています。
これからの文章は、昭和2年という時代背景でのお話としてご理解下さい。
また、要点を抜き出しての文章ですので、前後の文章とうまくつながっていないこともあると思いますが、ご理解願います。
「鈴木大拙の禪とは何か」 その1
宗教とは
はじめに、社会的事象として宗教を見るなら、一つの制度とも見られます。本山と末寺、檀徒、信徒というように組織づけられていて、組織の上から社会生活を構成する1分子であります。
今日だいぶやかましい問題になっている宗教法案というものも宗教を一つの社会生活の1事象と見て、初めてその必要が発生したものと考えられます。
次に、宗教を儀式の面から観察すると、経文の読み方、服装とか作法、お祭りなどと儀式のない宗教は宗教でないともいわれています。
禅宗ではよく「本来無一物」などというから、本来無一物のところになにゆえに煩雑なる儀式が必要なのかと、世間では疑う人もあるが、いかにしても宗教には儀式が不可欠であります。
また寺院の建築なども一つの儀式と見られます。キリスト教イスラム教その他の宗教と仏教の寺院建築とを比較するとその内面的差異が直ちに建築物という外形にも顕れています。その各宗教的感情生活の相違が如実に形骸(けいがい)の中に包まれているということは、宗教の特殊性を知る上に誠に便宜でもあり興味あることでもあります。
- 【前のページへ】
- 【善勝寺だよりトップへ】
- 【次のページへ】