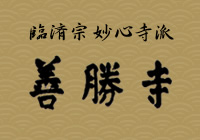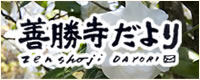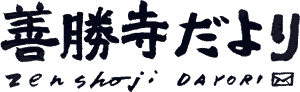 |
善勝寺だより 第123号令和5年6月15日発行発行責任者 明見弘道 (2ページ) |
 |
|---|
東光山ミニ法話

怨親平等(おんしんびようどう)
今年のお盆の施本は『ゆるすこころ』
円覚寺の管長、横田南嶺老師が書かれたものです。この本は春の彼岸にも施本としましたが多くの方にお読み頂きたくお盆も用意いたしました。
この本を読んで頂ければおわかりいただけますが、右の「怨親平等」のことが書かれてあります。
身内も他人も平等に接するという意味で「華厳経」にも用いられています。
鎌倉時代元(げん)の大軍が2度にわたり日本に攻めてきました。文永の役(えき)と弘安の役です。この時日本の多くの武士と元の多くの兵士が亡くなりました。
その後円覚寺の「仏光国師」(無学祖元禅師)は、「怨親平等」といって敵も味方もも区別せずに、多くの兵士を平等に供養されました。
一遍上人が開かれた時宗(じしゅう)の遊行(ゆぎよう)寺には室町時代の上杉氏と足利氏との戦(いくさ)で亡くなった兵士のために敵味方供養塔(怨親平等碑)が建立されています。
また、島原の乱のあとでは殺された切支丹(きりしたん)側の人々の冥福さえも念じて、怨親平等の法要が行われています。
このように、敵も味方も平等に供養するということが行われてゆくようになったのです。
「実にこの世においては、怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息(や)むことがない。怨みをすててこそ息む。これは永遠の真理である」(法句経)とあります。
昭和26年サンフランシスコ講和会議でスリランカの代表ジャヤワルダ氏はこの仏陀の言葉を引用して演説され、日本に対する賠償請求権を一切放棄すると明言されました。
戦時中、スリランカに駐留するイギリス軍の軍事施設を日本が空爆したため、スリランカは日本に対し賠償を請求する権利を持っていましたが、その権利をすべて放棄するというものでした。釈尊の教えがこのようなかたちで生かされていたのです。
ダライ・ラマ14世は「砂に1本の線を引いたとたんに、私たちの頭には『あちら』と『こちら』の感覚が生まれます。この感覚 が育っていくと本当の姿が見えにくくなります。」と仰せになっています。本来自分も他人もないのに、たった1本の線を引くことで差別が生まれるのです。そうするとこちらは自分のものという思いが生じてしまいます。
が育っていくと本当の姿が見えにくくなります。」と仰せになっています。本来自分も他人もないのに、たった1本の線を引くことで差別が生まれるのです。そうするとこちらは自分のものという思いが生じてしまいます。
『ゆるす心』というのは、敵をも許すというよりは、敵と味方という区別をしない心であります。みんな同じ人間なのです。みな同じ命を生きているのだという自覚のもとに、自他を区別しない心を持つことが大切です。
「ゆるすこころ」より |
ご注意下さい
葬儀の案内で、お気を付けて頂きたいのは「火葬の時間」です。
葬儀式には間に合わないが、せめて火葬には立ちあってお別れをしたいという方はあります。
『午後1時火葬』となっているので、1時までに火葬場に行けば良いと思いがちですが、実際は30分前には火葬されます。火葬場によって違いはありますが、「みずほ斎場」の場合、1時火葬というのは、12時15分には入ることができ、お別れの焼香をしてすぐ火葬されます。会葬者の方で「みずほ斎場」で待ってるなどという方には
よく確かめてお伝え下さい。
- 【前のページへ】
- 【善勝寺だよりトップへ】
- 【次のページへ】