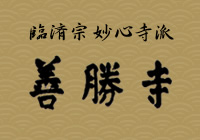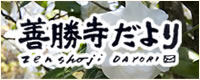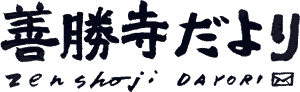 |
善勝寺だより 第121号令和4年12月22日発行 |
 |
|---|
『鳴鐘(めいしよう)の偈(げ)』と『聞鐘(もんしょう)の偈(げ)』
善勝寺の梵鐘(ぼんしょう)は戦時中、国に供出(きょうしゅつ)し外されたままになっていましたが、故熊田応其兼務住職の念願で、昭和63年に再鋳されたものです。
鐘の真下、石板に刻まれていますのが「鳴鐘の偈」であります。
三途八難(さんずはちなん) 息苦停酸(そっくじょうさん)
法界衆生(ほっかいしゅじよう) 聞声悟道(もんしょうごどう)
「どうか、この鐘の声を聞いた全ての生きとし生ける者が、それを縁として三途八難の苦しみから解放され、真実の道を悟りますように。」と願って鐘を鳴らすのですが、簡単に言うと「みんなそれぞれ幸せに暮らせますように」と願って鐘を撞きます。
他方「聞鐘の偈」は鐘を聞く側の心得です。
一聴鐘声(いっちょうしょうしょう) 当願衆生(とうがんしゅじょう)
脱三界苦(だっさんがいく) 速証菩提(そくしょうぼだい)
「一度、鐘の声を聞いたならば、全ての生きとし生ける者と共に迷いから生じる苦しみを克服して、仏弟子としての生き方を全うしよう。」と願って鐘の声を聞きます。
善勝寺の梵鐘には、鐘を打つときに撞(しゆ)木(もく)が当たる箇所の上二行にこの文字が書かれています。「一聴鐘声」は「一打鐘声」と、あえて鐘を打つ側の立場になっています。
普段「寺の鐘」と言いますが、正しくは「梵(ぼん)鐘(しよう)」であります。梵(ぼん)とはインドの古い言葉で「神聖で清浄なもの」を意味します。また鐘の音を梵音(ぼんのん)とも言い、梵鐘は仏様の声を表すものとされます。つまりありとあらゆる所に届く音なのです。
前のこの「善勝寺便り」にも書きましたが、線香や焼香したときの煙(香り)は仏様のお使いであり、思いがあらゆる所に届きます。それと同じように、鐘を打つ者の思いは、鐘の音に乗って故人であっても、遠く離れている方であっても、その思いを伝えてくれます。
善勝寺の梵鐘は夜間や特別な行事の時をのぞき、自由に撞くことができます。墓参の時など思いを込めて撞いて下さい。当寺の鐘はとてもいい音がします。きっと応其和尚の優しい心が鋳造の時練り込まれているからだと思っています。
撞木を引いて、力を入れて撞こうと思わないで、撞木の重さに任せるといい音がします。15秒ほど余韻を静かに聞いてから、次を撞きます。自然と心が静まってきます。
みんなそれぞれ幸せでありますようにお祈り申し上げます。
役員会議事録より
12月10日午後5時から、善勝寺庫裡に於いて、
来年度の予算を審議することを主な議題として『定例役員会』を開きました。
以下審議・決議内容を報告します。
- 現状報告。
今年度4月から11月末日までの会計収支などを報告。 - 「東光山合同船」増設に当たり、本体工事施工業者選択の件。
3社の見積もりを精査し、「クリタ石工芸」に依頼することを決定。 - 令和5年度行事・事業計画。 除夜・修正会・施餓鬼会・彼岸会などは、
今年度に準じて行こととし、行事に関する案内は、住職に一任する。 - 「令和5年度一般会計予算」(案)は、原案通り承認されました。
(以上)
- 【前のページへ】
- 【善勝寺だよりトップへ】
- 【次のページへ】